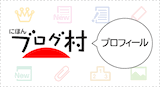|
2020/7/12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労使コミュニケーションは良くなっているか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 6月18日、厚生労働省が2019年「労使コミュニケーション調査」結果を公表した。
この調査は、労使間のコミュニケーションの方法や運用状況等の実態を、事業所側と労働者側の双方から明らかにするもので、5年ごとに行われている。 そもそも労使間のコミュニケーションとは何かだが、労働組合と会社との話し合いといった狭い意味だけでなく、自己申告制度や面談制度、経営者からのアナウンスや朝礼、ミーティング、上司との会話など広く職場のコミュニケーションを指すものと解される。 調査では、さまざまな質問項目があるのだが、ここでは労使間のコミュニケーションが良くなっているかという観点から、過去の結果も踏まえて確認してみよう。 事業所における労使コミュニケーションがどの程度良好であるかについての労働者の認識は以下の通りである。
調査年ごとに良好度が高まっていることがわかる。15年前に比べて20ポイント以上の改善で、労使間のコミュニケーションは確実に改善しているというのが労働者の認識である。 それでは、良好度について詳細を見てみよう。カッコ内は2014年の数値である。 まず、企業規模別では、 ・5,000人以上 62.2(50.6) ・300~999人 49.6(48.4) ・30~49人 38.7(28.0) と規模が大きいほど、コミュニケーションが良好なことがうかがえる。 男女別では以下のように差はない。 ・男性 50.7(44.3) ・女性 51.1(43.0) 就業形態別では、以下の通りで嘱託を除いてそれほどの差はない。 ・正社員 51.8(44.1) ・パート 47.9(44.6) ・契約社員 49.4(※) ・嘱託 36.7(※) ※2014年の契約社員・嘱託の数値は、「正社員・パート以外の労働者」というくくりで38.1 役職別では次の通りである。 ・課長クラス以上 54.4(64.4) ・係長クラス 52.3(48.1) ・役職なし 49.7(39.1) ここで、2014年との差異に注目してほしい。係長クラス、役職なしはプラスになっているのに対し、課長クラスはマイナス、しかも10ポイントも減少している。全体にプラス傾向にある中で、非常に目立つ事象である。人手不足の折、マネジャーとしての役割に加えてプレーヤーの役割も増え、コミュニケーションの時間が取れなくなっているのかもしれない。 役職別では、もう1つ興味深い傾向がある。2004年の良好度を見ると、 ・課長クラス以上44.1 係長クラス35.0 役職なし22.9 となっている。2019年は、2004年と比べて課長クラスは約10ポイントの伸びに対し、係長クラスは約20ポイント、役職なしは約30ポイントと大きく伸びていることがわかる。このところの労使コミュニケーションの進展は、非管理職での活発化に負うところが大きいようだ。 労使コミュニケーションが良くなっている要因としては、 ・コミュニケーションを活発化させることに企業が積極的に取り組んでいること ・社員にもコミュニケーション重視の意識が高まっていること などが考えられる。かつてのように比較的安定した経営環境のもと、同質の人材によりあうんの呼吸で仕事が進められた時代と違い、複雑かつ変化の速い現在の環境を多様な人材で乗り切っていくには、細やかなコミュニケーションが求められる。これからの時代は労使コミュニケーションを良くせざるを得ないというのが実態かもしれない。 にほんブログ村に参加しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |