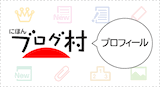|
2020/4/27
|
|
執行役員とは~その1 |
|
|
執行役員制を採用する企業は多い。 日本監査役協会の調査によると、2018年の監査役会設置会社の執行役員制の導入割合は、全体で62.5%、非上場企業で53.0%、会社法上の大会社以外で46.2%となっており、増加傾向にあるという。筆者の経験でも、100人以上の企業では執行役員制をとる会社が結構あると感じる。 あらためて執行役員とはどういうものだろうか? 執行役員は会社法上の制度・機関ではないため、内容も企業により千差万別だが、基本となるのは1997年に制度を初めて導入したソニーの定義だ。同社の株主総会議案書で次のような説明をしている。
取締役(会)の機能には大きく分けて、①経営に関する意思決定、②①に基づく業務執行、③業務執行が適切になされているかの監督、の3つがある。執行役員制度は、このうちの②を切り離して執行役員に委ね、取締役は①と③に専念する仕組みだ。 1997年といえば平成不況の始まりの年で、日本経済を暗い影が覆いつつあることをソニーの経営陣も察知していたに違いない。当時、取締役が38人いたそうだが、これでは取締役会がまともに機能せず、危機への機敏な対応は困難となる。取締役の人数を削減する方策として、考え出されたのが執行役員制である。 取締役を外れる社員のプライドを保てるよう「役員」という言葉を取り入れたところに同社のネーミングセンスの高さがうかがえる。ちなみに当時の社長は、執行役員となる取締役の家族に決して降格させるわけでなく待遇も変わらない旨の手紙を送ったとのことだ。制度導入により取締役は10人となり、34人が執行役員に就任したという(うち、7人は取締役兼任)。 以後、導入企業は相次いだわけだが、一方で、執行役員を廃止する企業も少数ながらある。2016年8月23日の日経新聞では、その理由として、次の3つを指摘している。 ①名ばかり役員を減らすことで組織の風通しをよくするため ②企業規模に比べて幹部が多すぎるため ③指揮系統が複雑になり機能していなかったため 要は執行役員制の形骸化ということだろう。社長の業務執行の補佐というよりは、単に部長以上・取締役未満の社員を処遇するポジションとして運用されているケースを筆者も見かける。中には、対外的な見栄えのためだけと思われる企業もある。そういった企業で弊害が顕著となり、廃止に至ったと考えられる。 以上、執行役員とは何か、基本的なことを確認した。次回は、執行役員と会社法の関係、導入の際の検討事項など、導入する際のポイントを整理したい。 にほんブログ村に参加しています。
|
|
| |