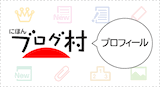4月20日の共同通信で、学生の就職活動や企業の採用選考で、生成AIを活用する動きが広がっていることが報じられていた。記事では、自己PR文を短時間で作成するアプリやエントリーシートのガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の文章を自動作成するアプリなどを取り上げている。また、企業側の取り組みとして、ローソンが導入した「AI面接官」を紹介している。
AIが作成したエントリーシートをAIが選考する。あたかもキツネとタヌキの化かしあいのようだが、こういった動きは、今後ますます活発化することが予想される。どのような動きがあるかを学生・企業、双方の視点から見てみよう。まず、学生側のツールとしては以下のものがある。
・履歴書・エントリーシートの言葉遣いやキーワード、構成などをアドバイスするAI添削サービス
・表情、声のトーン、話すスピードなどを分析し、フィードバックを行うAI面接トレーニング
・本人に合う企業や職種を推薦するAI企業マッチングサービス
・AIチャットによるキャリア相談
・本人の関心に応じた最新の求人を届けるAI求人情報配信
一方、企業側のツールには以下のものがある。
・応募者のエントリーシートをAIが読み込み、キーワードや構成、論理性などを評価するAIによるESのスクリーニング
・表情、声のトーン、話す内容をもとにスコア化するAI面接
・ウェブ上で回答した性格診断や能力テストの結果をAIが解析AI適性検査(性格・能力テスト)
・説明会予約、質問対応、選考の進捗案内などをAIがチャットで行うAIチャットボット
・内定後のフォロー状況や性格データをもとに、早期離職のリスクを予測し、フォロー計画を立てるAIによる内定者フォローや早期離職予測
学生も企業も、このようなAIツールを活用すれば効率的に活動できることは間違いない。とはいえ、現状、あまりにAIに頼り過ぎるのは危険である。便利さの裏にある落とし穴に留意しなければならない。
学生側の落とし穴としては、内容の薄さと画一性が挙げられる。一見きれいにまとまってはいるものの、表現が画一的で自分らしさが希薄となり、他の学生と似た内容になりがちとなる。いくら形が整っていても、具体的な中身を自分の言葉で語ることができなければ、薄っぺらさを面接者に見抜かれてしまう。
企業側の落とし穴としては、過去の成功パターンに寄りすぎるリスクと、学生の本来の力を正しく測れないリスクである。
学生の選考に使うAIは、過去の内定者データや選考結果をもとに学習している。そのため、どうしても過去に選ばれたタイプ(熟考型やリーダー型など)に似た学生を高く評価しがちとなる。その結果、新しいタイプの人材(クリエイティブ型やロジカル型など)を取りこぼすリスクがある。AIだからといって、必ずしも公正な選考ができるわけではないのだ。
また、AI面接は表情や声のトーンを評価するため、緊張しやすい学生やオンライン環境が整っていない学生に不利になる場合がある。AI適性検査も、形式に慣れた学生が高得点を出しやすくなる。
AIは効率化の手段に過ぎない。学生も企業も、コアの部分は人間の頭で考えるようにしないと、期待する成果は得られないということだ。