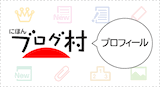前回、自己評価の高い社員は、結局のところ自身に多くの損失をもたらすことを述べた。「自業自得なのだから放っておけば」という考え方もあるが、表面的にはズルをしているように見えて、周囲には少なからぬ影響がある。不公平感を持つ人もいるだろうし、評価制度に対して不信感を抱く人もいるだろう。そして何よりも、本人のためにも望ましいことではない。やはり事態を放っておくのはよくない。今回は、上司として自己評価の高い人にどのような指導をすればよいか整理してみたい。
まず思い浮かぶのは、単純に「自己評価が高すぎるので評価を下げてほしい」といった指導だが、効果は期待できない。本人としては正当な評価と思っているのだから、納得してもらえる可能性は低い。仮に「そうですか。わかりました」と答えたとしても、本心は納得していないので、改善は期待しないほうがよいだろう。これまで以上に、いい加減な自己評価となる恐れもある。
では、どうすればよいか。基本的には、客観的な視点を持たせる指導が効果的である。以下のようなアプローチが考えられる。
1. 自己評価の根拠を明確にさせる
まずは、「なぜその評価をつけたのか?」を本人に説明してもらう。評価の根拠を明らかにするということだ。根拠のない過大評価を防ぎ、論理的な自己認識を促すことが目的である。このとき注意したいのは詰問調にならないことだ。取り調べのようになってしまうと、感情的な反発を引き起こし、是正できることも是正できなくなる可能性がある。
2. 具体的なフィードバックを行う
評価者が具体的な評価の根拠を示しながらフィードバックを行うことも基本だ。評価のギャップを数値や事実で示す。主観的な評価ではなく、客観的な視点を持つことの重要性を評価者自ら実践してみせる。
3. 成長のための視点を持たせる
前回の自己評価を高くすることのデメリットでも指摘したが、「自己評価を高くすること=成長機会を逃すこと」を伝える。自分の課題を正しく認識できる人が成長できることを説明する。
4.自己評価の目的を再確認してもらう
評価というのは基本的に自分以外の別の人が行うものである。人事評価で、あえて自己評価をしてもらうのは、能力の発揮度や業績の到達状況を自ら客観的に把握し、今後の能力開発に役立てるためだ。自己評価は、社員を「査定」するためのものではなく、「自らの成長」のためであることを理解させる。
5.正しい自己評価がリーダーに必要なことを理解してもらう
人を正しく評価できるかどうかは、リーダー・管理者の重要な適性の1つである。他者を適正に評価するには、まず、自身を適正に評価できることが前提となる。正しい自己評価ができるかどうかは、リーダー・管理者として、人のマネジメントができるかの判断材料となる。会社は、その点をしっかり見ていることを説明する。
6.360度評価(多面評価)を活用する
360度評価(多面評価)を実施しているのであれば、部下、同僚、他部署の上司など多方面からの評価を共有する。評価者だけでなく、他者も評価者と同様の評価をしているのであれば、説得力は高い。自己評価の高い人も納得せざるを得ない。その上で、「他者からの評価をどう受け止めるか?」を本人に考えさせる。
自己評価の高い人は、仕事には意欲的で、達成志向や上昇志向が強い人が多い。それを逆手に取り、根拠のない高い自己評価は、達成志向や上昇志向の妨げとなることを認識してもらうことだ。多分、1度言ったくらいでは変わらないかもしれないが、上記のアプローチを幾度か繰り返すことで改善は期待できる。地道な作業だが、そこは上司としての職責といえる。
もっとも、残念ながら、いくら指導をしても改善できない部下もいる。それはそれで仕方がない。前回指摘したように結局は本人の損になると思うのだが、それも部下自身の選択と割り切るしかない。