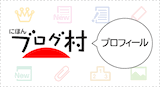|
2025/6/22
|
|
役員の労働者性 |
|
|
6月11日の共同通信に、建設会社の役員の死亡について労災が認定されたとの記事が掲載された。詳細は以下のとおりである。 ・2017年5月、千葉県の建設会社の専務取締役だった男性(当時66歳)が急性心筋梗塞で亡くなった。 ・会社の従業員数は約40人で、男性は代表取締役に次ぐ立場にあった。 ・週休1日で主に現場監督として働き、直近2~6カ月の残業は月平均100時間を超え、「過労死ライン」とされる80時間を上回っていた。 ・工事の受注や人員配置を決める「業務執行権」が代表取締役にはあったが専務にはなかった。 ・男性は実質的に労働者だったとして、18年9月に労災認定された。 通常、会社の取締役や監査役といった役員は「使用者」に該当し、労働基準法上の「労働者」とはならない。労災保険法では労働者の定義を定めていないが、法律の目的・趣旨から労基法の労働者と同じと解されている。したがって、役員は原則として労災保険に加入できない。本件のように役員(しかもナンバー2の専務取締役)が労災認定されるのは極めて異例の事態といえる。 あらためて労働基準法上の役員の労働者性について整理してみよう。 労基法9条では、『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』とされている。企業の役員の「労働者性」は、この規定に基づき、以下の2つの基準で判断される。 ①労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか ②報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか この2つの基準は、総称して「使用従属性」と呼ばれる。「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断される。 共同通信によると、本件の認定に際しては、同僚らの証言や男性が自主的に記録していた出勤簿が重要な役割を果たしたとのことだ。上記のうち「労務提供の形態」が労働者性の根拠になったと思われる。 役員であれば労働法は適用されないので、労働時間・休日も気にしなくてよく、残業代も支払わなくてよい。雇用保険も労災保険も加入しなくてよいし、解雇の制限もない。煩雑な労務管理から解放される究極の手段として、「社員の役員化」が用いられることもある。実際、ほとんどの社員を取締役に就任させ、その数が400人にものぼった異常な会社が以前話題となった。 本件は、そのような脱法目的の役員登用ではなかったと思うが、中小のオーナー企業では、役員であっても実態として労働者化しているケースがあると考えられる。人員の関係から、ある程度は現場の業務を担ってもらうのは仕方ないにしても、それとは別に、本来の役員の業務を遂行してもらっているかどうか、この機会に見直すことが望ましい。 にほんブログ村に参加しています。 |
|
| |