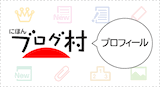現在、定年年齢は60歳以上と高年齢者雇用安定法で定められている。法定されたのは1994年のことで、施行は1998年である。すでに30年近くが経過している。次に定年年齢が引き上げられるとしたら65歳ということになるだろう。では、実際に引き上げは行われるのだろうか? 「引き上げられる」「引き上げられない」それぞれの根拠を踏まえて検討してみよう。
まず、引き上げが行われる根拠としては、次のものが考えられる。
① 少子高齢化と労働力不足
生産年齢人口(15~64歳)が減少し続けており、シニア層の活用が不可欠となっている。特に中小企業や地方では、65歳まで正社員で働いてもらうことが現実的な対策となっている。
② 社会保障制度の持続可能性
公的年金の支給開始年齢が65歳となっているため、それ以前に退職しても無収入期間が生じる。60歳定年では生活保障の観点から制度との齟齬が生じる。
③ 70歳までの就業機会確保措置との関係
2021年に「70歳までの就業機会確保努力義務」が定められた。定年後の雇用はどちらかと言えば「ほどほどに働く」感が労使とも強いが、60歳定年だと、それが10年もの長きにわたることになる。
④ 平均寿命・健康寿命の延伸
現代では、65歳と言っても老人のイメージはない。正社員として仕事を継続できる体力・能力を持つ人が多く、就労意欲も高い。
⑤ 同一労働同一賃金の流れとの整合性
定年後再雇用では賃金が大幅に下がるケースが多く、処遇格差是正の観点からも、再雇用ではなく「定年延長」による雇用維持が整合的である。
⑥ 公務員の定年年齢引き上げ
2023年度から、公務員の定年年齢引き上げが始まっており、2031年度に65歳定年となる。公務員の定年引き上げは、法制化の布石とも考えられる。
一方、65歳定年への引き上げは行われない(引き上げるべきでない)と考える根拠は次のとおりである。
① 企業の人件費負担の増大
日本では年功序列型の企業がまだ多く、定年を65歳にすれば、高齢社員の高い賃金水準が長期化する。人件費と業績がマッチせず、企業の体力が低下していく恐れがある。
② 継続雇用制度が既に整備されている
現行法では、60歳定年後も65歳までの継続雇用が企業に義務付けられており、制度的には空白がない。法的には実質的に65歳就業が担保されているため、新たな定年延長は不要ともいえる。
③ 高年齢者の職務適応力の個人差
加齢による体力・認知機能の低下、ITスキルなど職務適性の問題から、画一的に65歳まで働かせることが組織運営上適切とは限らない。
④ モチベーションと成果のギャップ
モチベーションが維持されないまま居残る高齢社員が増えると、業績や若手育成に悪影響を与えかねない。
⑤ 雇用の世代間バランス悪化
高齢者の在籍期間が延びることで、若年層の採用抑制・出世の遅れ・世代交代の停滞が起きやすい。社員のモラールに悪影響を与えるとともに、組織の高齢化・硬直化を引き起こす。
⑥ 高齢者本人の就業意欲の差
全員が長く働きたいわけではない。健康や家族事情から「60歳で一区切り」が望ましいと考える人も一定数おり、選択の自由を残すべきとの考えもある。
さて、どちらの根拠が妥当か? 筆者は、65歳定年は「行われない」と考える。法制度として65歳定年を義務化するのではなく、現状の60歳定年+継続雇用または定年延長の選択肢併存のままにしておく方が、「企業の多様性」や「個人の事情」に柔軟に対応できるという立場である。
もっとも、20年後の60歳は今の55歳と同程度の健康状態・活動力を有している可能性が高い。そうなると、60代前半は十分に労働可能な年齢とみなされ、65歳までの引き上げがなされるかもしれない。