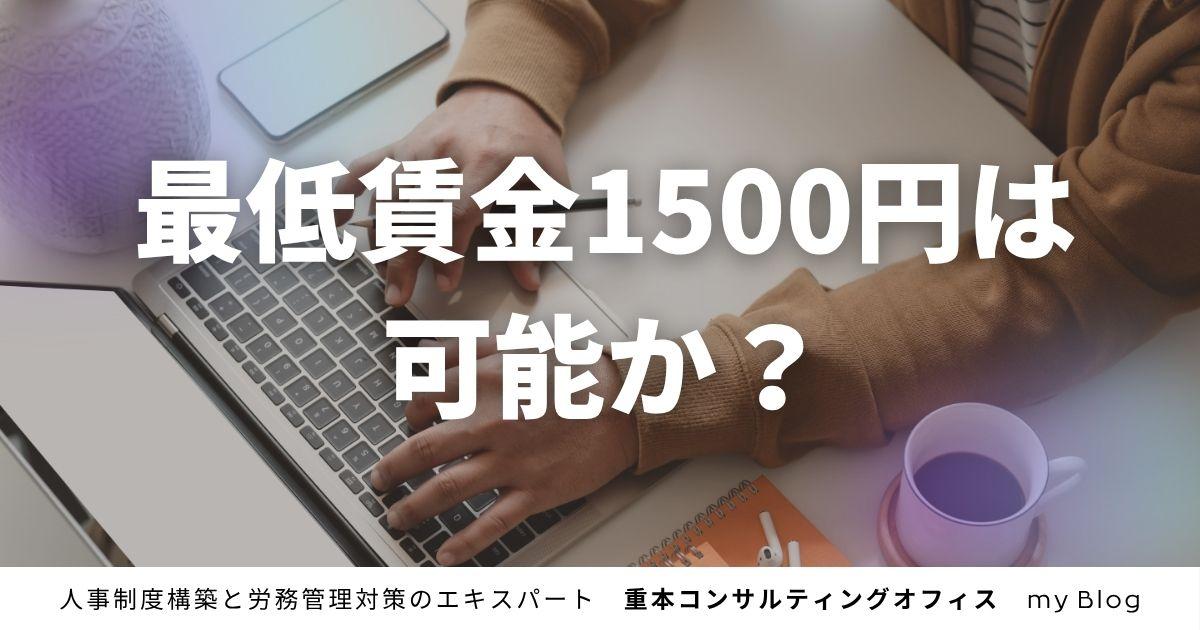
政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げている。2025年は6.0%アップなので、今後、毎年0.7ポイント上昇させることで、29年度に1,507円になるという目算である。ただ、これだと29年度は8.8%ものアップとなるなど、相当に高いハードルと言わざるを得ない。
当の企業はどのように考えているか。東京商工リサーチが10月16日に公表した「最低賃金引き上げに関する企業アンケート」結果によると、「あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?」との質問に、「不可能」は最多の49.2%だった。ほぼ半数の企業が、最低賃金1,500円への対応は困難と回答している。ちなみに、「すでに時給1,500円以上を達成」は17.3%、「可能」は33.3%である。
それでは、どうすれば可能になるだろうか。「不可能」と回答した企業に、「どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)」を質問すると、「賃上げ促進税制の拡充」46.7%がトップで、以下、「生産性向上に向けた投資への助成、税制優遇」44.2%、「低価格で受注する企業の市場からの退場促進」27.8%、「解雇規制の柔軟化」27.58%、「販路拡大に向けた投資への助成、税制優遇」26.96%となっている。
1位、2位、5位は税制上のメリットだが、中小企業の3分の2は赤字とされており、恩恵を受けられる企業は多くはない。3位の「低価格で受注する企業の市場からの退場促進」は、要は競合が少なくなればよいということだが、最低賃金1,500円に苦慮する企業は、どちらかと言えば“退場促進”される側に属していると考えられ、自分で自分の首を絞めることになりはしないか。
効果が期待できそうなのは「解雇規制の柔軟化」である。ところで、一見関係がないように見える「解雇規制の柔軟化」と「最低賃金1,500円」がどう結びつくのだろうか。これは、解雇規制を柔軟化することで、企業は賃上げをしやすくなるという構図で考えればよい。具体的に説明してみよう。
日本は世界的に見ても、解雇規制がかなり厳しい部類に入る。そのため企業は、一度雇った社員を簡単に減らせないという前提のもとで人件費を決めている。結果として企業は、将来の業績悪化リスクを見越して賃上げに慎重になる、正社員の賃金を抑え非正規雇用や外注で調整する、といった行動を取りがちとなる。つまり、「解雇できないから賃上げもしにくい」という構造が生じる。
一方で、解雇規制が緩和されると、企業は経営環境に合わせて人員調整をしやすくなる。そうすると、将来の固定費リスクが下がるため、安心して賃上げを行いやすくなる、不要な人員を抱え続けるコストを削減でき、生産性の高い人材により高い報酬を支払えるようになる。
このように、解雇規制が柔軟な場合は、解雇規制が厳しい場合に比べて、企業の人件費の固定化リスク低くなることや、賃上げ姿勢が積極的・成果反映型になることで、賃金上昇が促されるというロジックである。
もっとも、解雇規制の柔軟化が行われるかと言えば、「当面はない」というのが現実である。まず、最低賃金1,500円の実現を求める労働側も、解雇規制の柔軟化には猛反発をしている。新首相に就任した高市総理は、「労働時間規制の緩和」を打ち出すなど、財界よりの姿勢が見られるが、解雇規制の緩和には消極的である。2024年の自民党総裁選で、小泉候補が表明した解雇規制緩和に反対している。
ということで、当面の間、解雇規制の柔軟化は検討されそうにない。税制優遇等の他の施策も効果は限定的である。2020年代の最低賃金1,500円達成はいばらの道と言わざるを得ない。